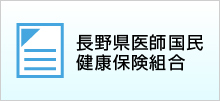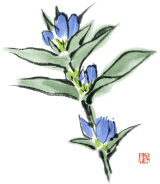令和7年度長野県医師会事業計画
はじめに
令和6年は1月1日に石川県能登半島地震が発生し、翌日には羽田空港での飛行機同士の衝突事故等、災害や事故で明けた年でした。能登半島地震では長野県下の医療機関も日常診療で御多忙の中、救急災害の現場で被災された地域の方々のために御尽力を頂きました事に対して長野県医師会としても改めて感謝申し上げます。発災の際の会員医療機関の被災状況の把握と復興支援の重要性を再認識しました。今後も救急災害医療について日本医師会とも協力して、県民の生命と安全な暮らしを最優先に考えて実行してまいりたいと思います。
令和6年4月から医師の働き方改革がスタートしました。労働時間の上限規制などにより、今後、県内の医療機関において医師不足や地域医療提供体制の確保、特に救急医療提供体制への影響や本県の山間地やへき地での医師確保が困難となる事が懸念されます。これからも長野県や長野労働局との意見交換を行い問題解決に向けた方策などについて検討してまいります。
令和6年6月からの診療報酬改定では生活習慣病管理料の算定に関する医療機関へのマイナスの影響や従来の保険証の廃止に伴うマイナンバーカードへの保険証機能のひも付け等、民意を充分に反映した施策とは言えない部分があるかと考えます。医療DXに関しては各医療機関の実情をしっかりと把握して、行政や日本医師会とも密に連携をとり会員の先生方の日常診療に支障が生じないように、また、県民の受診時に問題が生じないように努めてまいります。
令和2年から毎年、新型コロナウイルス感染症の対応で会員の先生方には日常の診療業務に加え、予防接種や発熱患者への診察など、大変に御苦労をおかけしております。改めて感謝申し上げます。今後も新型コロナウイルス感染症のみならず新興感染症への対策に全力で取り組んでまいります。
長野県医師会では、救急災害への対応、医療DX、医師の働き方改革、医師看護師等の人材確保、新興感染症への対応、医業承継、医師会組織強化等へ積極的に取り組み、県民の生命と健康を第一に考え活動してまいります。
会員の先生方の日常診療がより良いものとなりますように行政や日本医師会をはじめ、関東甲信越医師会連合会、郡市医師会と連携を密にしながら次に掲げる重点項目を中心に各種施策を推進してまいります。
重点項目
1.新興感染症等の発生・まん延に備えた地域医療提供体制の構築
新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」上の五類感染症に位置付けられ、ポストコロナに向けた地域医療提供体制づくりが進められ、令和6年6月より、平時から新興感染症等の発生・まん延に備えるため、長野県と医療機関等がその機能及び役割に応じて協定を締結する医療措置協定がスタートしました。これは新型コロナウイルス感染症対応の最大の体制と同程度の医療提供体制の確保を目指したもので、昨年8月31日時点で流行初期以降の発熱外来を除き、9項目中8項目で数値目標が達成され、各医療圏において、フェーズに応じた医療提供体制が迅速かつ円滑に構築できるよう健康危機対処計画に反映されました。
今後は、新興感染症が発生した際の影響にも留意しつつ、人口減少や高齢化の進行等、医療提供体制を取り巻く状況が徐々に変化することにも対応しなければなりません。地域の実情に応じた持続可能な医療提供体制の確保に向け議論を行い、平時から体制を整えておくことが一層重要となります。長野県において改訂される新型インフルエンザ等対策行動計画を踏まえ、適切な医療提供体制ができるよう、県と協議を進めてまいります。
(1)第8次保健医療計画並びに地域医療構想等への対応
令和6年度から第8次保健医療計画(~11年度)がスタートし、併せて医師の地域偏在・診療科偏在を解消するため、第8次医師確保計画に基づき医師確保に向けた取り組みが進められています。地域医療構想と働き方改革の取り組みを三位一体で進めるために引き続き地域の実情に沿った実効性のある事業の遂行を行政と密に連携し推進してまいります。
また、長野県における総人口の減少と高齢化が今後より一層進むとされており、医師の高齢化や後継者不足が問題となっております。県内における医師少数区域において住民が継続して医療を受けられるよう適切な医師の配置を県に依頼するとともに、後継者不足に悩む医療機関の医業承継が適切に図られるよう関係機関と協力してまいります。
長野県医師会は、これらの国における動向を注視するとともに、地域のニーズや人口減少に応じ、医療機関が共倒れすることなく、適切な医療提供体制へ収斂できるよう、各地域の調整会議を主導する立場の郡市医師会に対し、引き続き迅速な情報提供に努めるとともに、県地域医療構想調整会議に会長等役員が参加し、医師会としての意見を表明してまいります。
(2)医師・看護師確保対策への対応
長野県は、県全体の医師偏在指標が219.9(基準値:医師少数都道府県 228.0以下)であり、全国で36位の「医師少数県」であります。こうしたなか、開業医の高齢化や後継者不足に伴う診療所の廃院、在宅当番医や休日・夜間急病センター等の初期救急に対応する医師の減少、令和6年4月から施行された医師の時間外労働規制による地域医療提供体制への影響などの諸問題に対して、更なる医師の養成や確保、地域や診療科による医師偏在の解消が重要であります。
日本医師会では、医師偏在解消に向けた対応として、①公的・公立病院の管理者要件、②医師少数地域の開業支援等、③全国レベルの医師のマッチング支援、④保険診療実績要件、⑤地域医療貢献の枠組み推進、⑥医師偏在対策基金の創設の6つの取り組みを提言しており、様々な手段を駆使して複合的にこの問題に対応していく必要があるとしております。
また、国では、「新たな地域医療構想に関する検討会」等において、医師偏在対策として、早急に医師確保が必要な「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」の設定や「医師偏在是正プラン(仮称)」の策定などについて検討されております。
また、長野県医師会における看護師確保対策は、地域の医療機関において看護師の不足を解消し、安定した医療を提供するために重要な取り組みです。具体的な対策としては、県看護協会が運営する「県ナースセンター」の体制強化などです。新型コロナウイルスが五類感染症へ移行したとはいえ、治療や処置に関し負担減となった訳ではなく医療機関の看護職員不足は依然深刻な状況にあり、有料職業紹介事業者を利用した看護師確保が年々増加しており、それに要する紹介手数料が経営上の負担となっています。これらの対策を総合的に実施することで、看護師不足の解消や定着率の向上が期待できることから、行政や関係団体と協力しながら看護師確保の取り組みを進めてまいります。また行政に対し医師会立看護師・准看護師養成所への支援を継続して依頼し、長野県医師会としては郡市医師会負担軽減のための補助を引き続き行い、地域密着型の看護師、准看護師養成に今後も取り組んでまいります。
様々な社会状況の動向を注視しつつ、地域の実情に応じた医師及び看護師確保対策が図られるよう日本医師会や県と連携を取りながら対応してまいります。
(3)医師の働き方改革への対応
在宅当番医や休日・夜間急病センターは、開業医を中心に運営しておりますが、開業医の高齢化や後継者不足に伴う診療所の廃院などにより、初期救急に対応する医師が減少してきております。これに加えて、令和6年4月の医師の働き方改革施行により、休日・夜間急病センター等へ大学病院等から医師の派遣を受けることが困難な地域が出てきております。
医師の健康確保と労働時間短縮を行いながら、地域医療提供体制や救急医療提供体制が確保できるよう、長野労働局、長野県および長野県医師会の三者による意見交換会等の場を活用し、医師の働き方改革によって生じた課題等の情報共有や、宿日直許可の取得等を含め問題解決に向けた支援を行うための方策等について検討してまいります。
2.診療報酬改定及び医療DXへの対応
令和6年度の診療報酬改定率は、診療報酬(本体)がプラス0.88%でしたが、現在の物価高騰などを考慮すると、納得できる改定率とは程遠い結果であったことから、次回改定に向け、安定した医療機関の経営が可能となるよう日本医師会に対して提言してまいります。
マイナ保険証については、いまだ残る国民の不安などから利用率が低迷していますが、令和7年12月2日には健康保険証の使用に係る経過措置が終了し、医療機関の受付において更なる混乱が予想されることから、マイナ保険証の利用促進に向け、県や保険者に対して周知・広報に努めていただくよう要望するとともに、日本医師会にはカードリーダーの故障等不測の事態が生じた際も医療機関の受付において混乱が発生することのない方策の検討を要望してまいります。
政府は令和6年6月21日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2024」(骨太の方針2024)において、電子カルテの導入や電子カルテ情報の標準化等の整備・普及を強力に進めると示されているが、電子カルテや電子処方箋の導入には多大な経費が発生いたします。また、併せて厳重なセキュリティ対策をおこなう必要もあるため、更なる経費負担が生じることから、支援制度の整備について日本医師会や関東甲信越医師会連合会を通じて提言してまいります。
近年、国内外の医療機関を標的とした、ランサムウェアを利用したサイバー攻撃による被害が増加している状況にあることから、長野県医師会としてはサイバーセキュリティ対策について啓発、研修、広報等の活動を長野県警察本部と連携しながら推進してまいります。
3.地域包括ケアにおける在宅医療等の充実及びかかりつけ医機能への対応
地域包括ケアは、日常生活圏域での居宅等在宅医療提供体制の整備が重要であり、とりわけ医師を始め居宅等在宅医療に取り組む地域に密着した医療従事者の養成・確保が必要不可欠です。地域における保健・医療・介護・福祉など多職種間の連携を推進するために、かかりつけ医の役割は益々重要になっています。
また、複数の慢性疾患を抱える高齢者が増加する中で、かかりつけ医機能を担う医療機関において、予防や生活全般に対する視点も含め、継続的・診療科横断的に患者を診るとともに、必要に応じて適切に他の医療機関に紹介するなど、かかりつけ医機能を強化することが課題となっています。「日医かかりつけ医機能研修制度」などを活用し、かかりつけ医の養成と資質向上を支援してまいります。
令和7年4月より施行されるかかりつけ医機能報告制度については、都道府県が医療機関からの報告を受け、その情報を見える化するとともに、かかりつけ医機能報告を踏まえた協議を市町村等と連携しながら円滑に進めることとなっておりますが、地域住民が制度を理解し活用できるよう周知していくことが重要です。医療のフリーアクセスや国民の権利を守るため、引き続き日本医師会とともに動向を注視してまいります。
医療従事者の在宅医療への参入の動機づけと質の高い在宅医療継続に繋がる研修や、在宅医療を担う多職種との連携、在宅看取りに関する支援、県民の在宅医療に関する知識や理解を深めるための事業を、地域医療介護総合確保基金等を活用し実施します。
地域包括ケアの構築に向けては、県の第8次保健医療計画や第9期高齢者プラン、障がい者・医療的ケア児等への対策を踏まえ、保険者である市町村が地域の自主性や主体性に基づき作り上げていくことが必要となることから、各郡市医師会と市町村との連携を支援してまいります。
さらに、高齢者の虚弱(フレイル)予防は健康寿命の延伸を図る上で重要な課題であることから、研修会の開催などにより医療関係者などに対し啓発するとともに、行政による地域特性のある高齢者の自立を支援するための体制整備に協力してまいります。
人生の最終段階における医療・ケアについて、事前に医療・ケアチーム等と繰り返し話し合い共有するアドバンス・ケア・プラニング(ACP:人生会議)の、医療・介護の現場はもとより県民に対する普及・啓発を進めてまいります。併せて、リビングウィル(事前指示書)の地域における合意形成・多職種連携による仕組みづくりなどについて医療関係者へ情報提供するとともに、リビングウィル(事前指示書)の県民への普及・啓発に努めてまいります。
令和6年度に医業承継に関する連携協定を八十二銀行と締結しました。医業承継に関する様々な支援体制について周知するとともに、地域の医療提供体制の維持に繋がる活動をしてまいります。
4.研修事業による地域医療の質の向上
県内の医師が日進月歩の医学、医療を実践するための自己学習や研修を効果的に行えるよう、日本医師会の各種制度と連携し研修会を開催し、質の高い医療の提供に貢献します。
日本医師会生涯教育講座は、新専門医制度において専門医共通講習の単位として認められており、また診療報酬算定に必要な研修として位置づけられるなど、会員・非会員を問わず重要な制度となっています。引き続き各種研修会の開催により、会員の生涯教育単位取得を支援します。
なお、日本医師会生涯教育講座については、多くの医師が出席できるよう集合開催と併せWeb講習会を活用してまいります。
また、日本医師会認定産業医制度や認定健康スポーツ医制度に基づく認定医の養成や資質向上のための研修会を開催し、産業医活動や健康スポーツ医活動を支援します。
5.災害医療対策の推進・初期救急医療体制の支援
令和6年度に長野県第8次保健医療計画が策定されました。「長野県災害医療活動指針」は、平成23年に策定されていますが、第8次保健医療計画に沿った新たな災害医療活動指針の策定が待たれます。長野県医師会として、活動指針の刷新を注視するとともに、積極的に係わってまいります。新たな災害医療活動指針の策定に合わせて、長野県医師会の「長野県医師会災害時医療救護指針」の改定の検討をしてまいります。また市町村、広域連合、郡市医師会等医療関係機関、県保健福祉事務所の連携により2次医療圏毎に策定された「地域災害医療マニュアル」についても、県指針見直し等の内容を踏まえた改定となることから、関係郡市医師会と十分連携を図るように県に働きかけを行うだけでなく、郡市医師会の「災害医療マニュアル」や地域行政との協定の有無を把握し、郡市医師会への協力をしてまいります。
また、実際に発災の際、長野県医師会に求められる役割は、会員医療機関(診療所)の被災状況の把握と復興支援の2点です。被災地の会員医療機関の被災状況を「災害被害状況報告書」等を活用し、郡市医師会経由で的確に把握し、その被害状況を保健医療調整本部へ報告いたします。災害が起こった際の通信手段は大変重要です。しかしながら現在使用している衛星携帯電話は使い勝手が悪く、災害時の使用に不安が残るため、より安定して、使い勝手の良い新たな通信手段の確保を検討していきます。令和6年能登半島地震での医療対応を踏まえて、令和6年度JMAT研修会を開催しましたが、令和7年度は、令和6年度に行った研修会を踏まえて、JMAT活動の周知と基礎知識の習得のための研修会の開催を検討いたします。
これまで長野県では、郡市医師会と市町村が協力して、在宅当番医、急病センター制等による初期救急医療体制を構築し、その上で病院群輪番制による二次救急医療体制、7カ所の救命救急センターによる三次救急医療の整備が図られてきました。
ところが現在、県内では市町村単位での在宅当番医や急病センターによる初期救急医療体制の維持が、開業医の高齢化や在宅当番医を行うことができる診療所の減少、医師の働き方改革の影響などで、限界を迎えています。初期救急医療に対応する地域の広域化など初期救急医療を取り巻く状況が変化している中で、二次・三次救急の現場が疲弊しないために、初期救急医療体制を再構築すべき時期と考えます。
本来、初期救急医療は市町村で対応すべき問題ですが、各市町村のみでは課題の解決は困難で、広域での対応が必要となってきています。長野県医師会は、各市町村の初期救急の実情を理解するために、郡市医師会から地域の実情を伺い、その問題点を把握させていただき、二次・三次救急の現場への負担が過重とならないように医師会として長野県へ各地域に合った実効性のある初期救急医療体制の再構築の必要性を意見してまいります。
6.医療安全対策
「医療従事者の安全確保対策」としては、健康診断の確実な実施、感染症への適切な対応、メンタルヘルス対策、より良い職場環境の整備、労働災害・公務災害防止対応などがあります。
近年は、患者と医療者、異なる職種間、同一職種間などで発生する様々なコンフリクト(紛争・葛藤)を、当事者間で協働的に対応していくための「医療メディエーション(患者・家族と医療者など当事者間の対話の促進を通じ、相互の信頼回復と関係改善の場を形成、支援する仕組み)」が重要視されています。また、患者や患家等の立場の優位性を盾に、医師の診察や事務の対応に暴行、脅迫、暴言、不当な要求といった理不尽な迷惑行為のカスタマーハラスメントも多発しています。
令和7年度は、医療従事者が安心して安全で健康に働くことができるよう、患者相談窓口での対応、医療事故後の対応だけでなく、日常診療での患者への説明や医療従事者の教育に役立つ研修会等を計画してまいります。
7.医師会組織強化の推進
医師会の組織強化は喫緊の課題として取り組むべき最重要事項の一つです。
日本医師会では、三層構造である医師会の組織強化を「会員数の増加」と「質の向上」の双方の視点から取り組みを深めていくことで相乗効果を発揮し、医師会のプレゼンス(存在感)を図っていくことが重要であるとしております。
長野県医師会といたしましても、会員数の増加を図ると共に、各地域における課題等を共有し、課題解決に向けて組織として一致団結することが重要と考えております。
また、日本医師会では、会員情報システム(MAMIS)を構築し、これまで使用していた複写式の入退会・異動に係る届出書に代わり、会員個人がパソコンやスマートフォンによりWeb上で入退会や異動の手続きが行えるようになりました。長野県医師会といたしましても会員の入退会及び異動手続きの負担軽減や利便性の向上のため、令和6年12月23日よりMAMISの運用を開始いたしました。令和7年度からは日本医師会認定産業医や認定健康スポーツ医等の研修会の申込みや単位取得の確認もMAMISで行えるようになる予定であり、更なる会員の利便性の向上に対応してまいります。
また、県内臨床研修指定病院で実施している研修医オリエンテーションに役員が出席し、医師会活動等の紹介や入会案内を行う取組みについて、他県の成功事例を参考に令和7年度も継続してまいります。
事業遂行にあたっては、医師会活動の原点である郡市医師会との連携を密に協調を図り、日本医師会および関東甲信越医師会連合会との連携を保ちながら事業計画を着実に実行し、全会員の強い団結の下、県民の信頼が得られる医師会になるべく努力していく所存です。
事 業 項 目 と 主 な 内 容
Ⅰ.継続事業(公益目的事業)
-
1.学術研究事業
- (1)生涯教育推進事業
- 1)日本医師会生涯教育制度の円滑な推進
- 2)信州大学医学部との連携
- 3)郡市医師会及び関係医会と協力し会員の生涯教育を推進
- 4)長野県医学会の充実
- 5)長野県病院協議会等との連携
- 6)医師臨床研修への協力支援
- 7)各種学会・研修会等への協力
- (2)地域医療・公衆衛生対策事業
- 1)第8次長野県保健医療計画への対応
- 2)救急災害医療対策
- ・県並びに地域における災害時医療救護体制の充実強化
- ・医療救護班(JMAT)編成の推進
- ・JMAT研修会の開催
- ・地域災害医療コーディネーター養成支援
- ・初期・二次・三次救急医療体制充実への支援
- ・「長野県医師会災害時医療救護指針」の改定
- 3)感染症対策
- ・新興感染症対策の推進
- ・再興感染症(梅毒等)対策並びに啓発活動
- ・院内感染対策の推進
- 4)予防接種対策
- ・新型コロナウイルスワクチン接種等の促進
- ・市町村間相互乗入れ制度の推進
- ・定期予防接種の接種率向上の促進
- ・HPVワクチンの積極的勧奨の推進
- ・任意予防接種(百日ぜき対策を含む)の啓発活動並びに接種率向上の推進
- 5)長野県地域包括医療協議会及び各地区協議会への支援
- 6)特定健診・特定保健指導事業、後期高齢者健康診査事業の円滑な推進
- 7)健康スポーツ医学及びロコモティブシンドローム(運動器症候群)対策等に関する事業
- 8)臨床検査精度管理事業
- 9)各種健診対策
- 10)母子保健対策
- 11)長野県糖尿病対策推進会議の運営等
- 12)自殺対策、うつ病の診療・支援基盤強化事業の拡充・推進、児童虐待防止対策
- 13)麻薬対策、毒物・劇物等化学物質中毒対策
- 14)地域医療構想への対応
- 15)乳幼児等福祉医療給付事業への対応
- 16)警察の業務に協力する事業
- ・警察の業務に協力する長野県医師の会の運営、研修会の開催
- ・災害時を含む検視・検案体制強化への検討
- ・長野県死因究明等推進協議会への協力
- ・長野県警察本部との連携
- (3)がん検診対策事業
- 1)がん診療連携拠点病院の整備促進及びがん登録事業の推進への協力
- 2)健康づくり事業団等と連携した各種がん検診の受診率及び精度管理の向上
- 3)市町村が実施する対策型がん検診に係る精密検査実施医療機関一覧作成への対応
- 4)子宮頸がん検診及び乳がん検診市町村間相互乗入れ制度に係る協力医療機関一覧作成への対応
- (4)母体保護法指定医師関係事業
- 1)母体保護法指定医師関係事業の実施
- (5)勤務医対策事業
- 1)医師確保・医師偏在対策、勤務医対策の推進、医師の働き方改革への対応、「信州医師確保総合支援センター」への協力
- 2)信州大学医学部並びに県健康福祉部との連携
- 3)勤務医の医師会活動への参画の推進
- 4)女性医師支援の推進
- 5)長野県医学生修学資金貸与者の適正配置の推進
- (6)学校保健活動事業
- 1)学校保健施策に対する協力
- 2)学校保健に関する調査並びに対策
- 3)学校保健の普及啓発
- 4)学校医の研修
- 5)園医の実態及び課題の把握
- 6)関係機関及び各種団体等との連携
- (7)産業保健活動事業
- 1)長野県産業医学大会の開催
- 2)日本医師会認定産業医制度の促進及び同研修会の開催
- 3)職場における産業保健衛生活動の推進
- 4)労災保険診療の充実
- 5)関係機関及び各種団体等との連携
- 6)産業医学振興財団受託事業の実施
- 7)産業保健総合支援センター事業等への協力
- (8)地域包括ケア関連事業
- 1)地域医療介護総合確保基金への対応と関連事業の推進
- ・在宅医療に携わる医療機関の運営支援事業
- ・在宅医療の実施に係る拠点の整備事業
- ・在宅医療推進協議会の運営
- ・在宅医療普及啓発・人材育成研修事業
- 2)日医かかりつけ医機能研修制度の実施
- 3)医業承継の推進
- ・医業承継に関する研修会の開催
- ・在宅医療推進協議会の運営
- ・八十二銀行との医業承継に関する連携
- 1)地域医療介護総合確保基金への対応と関連事業の推進
2.助成事業
- (1)看護師等対策事業
- 1)医師会立看護師等養成所の支援
- ・国・県運営費補助金の確保、県医師会助成金の交付
- ・看護師、准看護師学院長会議の開催
- 2)県ナースセンター事業運営委員会への参画
- 3)医療従事者に対する生涯教育の実施
- 4)潜在看護師等の再就業の促進
- 5)准看護師試験への対応
- 1)医師会立看護師等養成所の支援
3.相談・支援事業
- (1)医療安全対策事業
- 1)医療メディエーション・カスタマーハラスメント対策等の講習会の開催
- 2)県の医療安全支援センターとの情報交換
- 3)医療事故調査制度への対応
- ・支援団体としての相談・支援事業の実施
- ・医療法に基づく支援団体連絡協議会の主宰・運営
- 4)長野県弁護士会の人権救済申立事件における医師への照会制度への協力
4.普及啓発事業
- (1)健康教育推進事業
- 1)健康教育用リーフレットの作成・配布
- 2)テレビ・ラジオを利用した健康教育番組の制作・監
- (1)生涯教育推進事業
Ⅱ.会員共益事業
-
-
(1)医療政策研究事業
- 1)日本医師会「医師の職業倫理指針」の周知
- 2)医療制度改革への対応、日本医師会、関東甲信越医師会連合会などとの連携
- 3)国民皆保険制度の堅持、控除対象外消費税対策、事業税非課税措置の存続他医業税制対策
- 4)医療政策研究会の開催
-
(2)医療保険対策事業
- 1)保険医療機関に対する指導における支援体制の充実
- 2)医師会主導による社保・国保両審査委員会の運営、関連情報の速やかなる提供
- 3)社保・国保両審査委員会との連携並びに医学的審査の充実
- 4)診療報酬改定に向けた問題点の整理、日本医師会、関東甲信越医師会連合会への提言
- 5)技術料を適正に評価した診療報酬体系の確立
- 6)適正な保険診療に向けた研修会の開催
- 7)保険診療に関する疑義解釈並びに情報提供
- 8)サイバーセキュリティに関する研修会の開催
- 9)県医師会及び郡市医師会保険部委員会相互の連携緊密
- 10)医療保険制度改革への対応
- 11)医療費適正化政策への対応
- 12)保険者協議会への協力
- 13)日本医師会及び関東甲信越医師会連合会との連携
-
(3)自賠責保険医療問題対策事業
- 1)自動車賠償責任保険医療問題検討委員会の開催
- 2)長野県損害保険医療協議会(保険者・診療側・審査機関三者構成)の開催
- 3)その他自動車賠償責任保険診療に係る情報の収集・提供
-
(4)介護保険対策事業
- 1)医療と介護の連携推進、介護保険地域支援事業への協力
- 2)介護保険の問題点の整理、日本医師会、長野県への提言
- 3)介護報酬改定に向けた問題点の整理、日本医師会、関東甲信越医師会連合会への提言
- 4)認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)への協力
- 5)地域包括ケア体制構築への協力
- 6)認知症サポート医養成研修及び認知症サポート医フォローアップ研修への協力
- 7)かかりつけ医認知症対応力向上研修への協力
- 8)地域医療介護総合確保基金を活用した介護事業所医療対応力向上研修事業
- 9)フレイル予防への対応
- 10)その他介護保険に係る情報の収集・提供
-
(5)医事紛争対策事業
- 1)医事紛争の未然防止対策の推進
- 2)医療事故紛争処理における日本医師会などとの連携
- 3)医療事故防止対策及び医事紛争処理の充実(産科など専門医の参画)
- 4)個人情報保護に係る医療機関等の対応
-
(6)広報活動事業
- 1)長野医報の充実・発刊
- 2)テレビ、ラジオ、リーフレットなどを利用した健康教育活動の充実
- 3)ホームページの充実
- 4)テレビ・SNSなどを利用した医療政策など対外広報活動の充実
- 5)各種情報の収集、情報管理の一元化及び迅速な伝達
- 6)マスコミ対策
- 7)ロゴマーク作成と活用の検討
-
(7)会員福祉厚生事業
- 1)会員の親睦対策
- 2)災害互助会事業の推進
- 3)所得補償制度の推進
- 4)日本医師会医師年金事業への協力
- 5)病院、診療所施設改善資金等の斡旋
-
(8)郡市医師会運営助成事業
- 1)郡市医師会助成費の交付
-
(1)医療政策研究事業
Ⅲ.受託事業
-
-
(1)長野県受託事業
- 1)長野県広域災害・救急医療情報システム運営事業
-
(2)長野県健康づくり事業団等受託事業
- 1)胃集団検診デジタル画像読影事業
- 2)がん検診における研究等事業
- ・胃検診読影技術向上に係る研修会等の開催
- ・超音波診断及びマンモグラフィー診断の精度向上のための研修会等の開催
- ・肺がん検診読影技術向上に係る研修会の開催
- ・前立腺がん検診事業における精密検査医療機関の把握
- 3)心電図解析管理事業
- ・児童生徒等心電図検査の県医師会解析プログラムによる自動解析
-
(3)長野県教育委員会等受託事業
- 1)県立学校児童生徒職員健康診断事業
- ・児童生徒職員心臓検診事業
- ・生徒職員結核健康診断事業
- ・県立学校職員定期健康診断事業
- 2)県立学校児童生徒心臓検診心電図再判読事業
- (4)妊婦一般健康診査等事業
-
(1)長野県受託事業
Ⅳ.会員互助事業
-
- (1)日本医師会認定登録事業
- 1)日本医師会認定産業医登録事業
- 2)日本医師会認定健康スポーツ医登録事業
- (2)日本医師会医師資格証発行の協力
- (3)保険料集金事務事業
- ・生命保険、所得補償保険、医師賠償責任保険等の保険料
- (4)保険代理店事業
- 1)損害保険
- ・所得補償、医師賠償、サイバー(情報漏えい含む)、自動車、交通事故傷害総合、産業医傷害 他
- 2)生命保
- ・がん保険、定期保険 他
- 1)損害保険
- (5)保険用紙斡旋支援事業
- (1)日本医師会認定登録事業
Ⅴ.その他事業
-
- (1)公益法人制度への対応
- 1)法人法に則った円滑な会務推進
- 2)公益法人会計基準の遵守
- (2)事務機能の充実・推進
- 1)会員情報システムの円滑な運営、会員名簿作成
- 2)受付文書等の電子保存化の実施
- 3)県医師会と郡市医師会間の情報交換の迅速化
- 4)郡市医師会向け文書管理システムを活用した事務処理効率化の推進
- 5)会員向け文書閲覧システムを活用した迅速な情報伝達の推進
- 6)Web会議システムの効率的な運用
- 7)会員の入退会異動に係る日本医師会会員情報システム(MAMIS)の利活用
- 8)事務処理の効率化
- (3)長野県地域包括医療協議会の活動推進
- (4)関連団体との連携
- 1)長野県医師国民健康保険組合事業への協力
- 2)(財)長野県アイバンク・臓器移植推進協会への協力
- 3)(財)信州医学振興会への協力
- (5)医師会組織強化に向けた取組み
- 1)医師資格証の取得の推進
- 2)若手医師、臨床研修医に対する医師会事業への理解促進並びに入会促進
- 3)医師会組織強化検討委員会の開催
- 4)郡市医師会医師会組織強化担当役職員連絡協議会の開催
- 5)研修医に対するオリエンテーションの実施
- (6)女性医師支援・ドクターバンク連携関東甲信越・東京ブロック会議への対応
- (1)公益法人制度への対応

 郡市医師会一覧
郡市医師会一覧 郡市医師会立
郡市医師会立 長野県医師会
長野県医師会