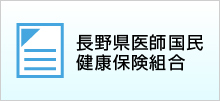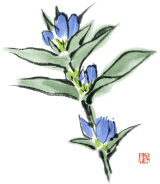「急変時DNAR」と記されたその意味 ―それは“しない医療”ではなく、“考える医療”の入り口―
カルテにふと目をやると、「急変時DNAR」の一文が記されていることがある。だが、それがいつ、どこで、誰と話し合って決められたのか不明なまま、ただ記載だけが残っていることはないだろうか。
DNAR――Do Not Attempt Resuscitation。日本語では「心肺蘇生を行わない方針」と訳されるが、その意味や背景が、医療者のあいだでどこまで共有されているだろう。ある医師は「高齢だから、終末期だから当然」と考え、ある看護師は「家族の希望で」と理解している。果たして、患者本人の意思はどうだったのか? 話し合いの場は持たれたのか? チーム全体が同じ認識を持っていたのか?
DNARの本当の意味は、「蘇生処置を行わない」という消極的な姿勢ではなく、患者の人生の最終段階において、その人らしく穏やかに過ごせるよう、最善のケアを選び取るという前向きな医療判断である。何もしないのではない。むしろ「何をするか」「何をしないか」を丁寧に考える出発点である。
終末期の患者に対して、どのような医療がふさわしいか―それを患者本人や家族、そして医療チームで繰り返し話し合い、積み上げていく先にDNARの合意がある。誰か一人の判断ではなく、チーム全体が倫理的な視点を持ち、同じ方向を見つめることが求められている。「急変時DNAR」と記す前に、私たち医療者自身がその意味を深く問い直す。そこから、ほんとうのチーム医療が始まる。
 郡市医師会一覧
郡市医師会一覧 郡市医師会立
郡市医師会立